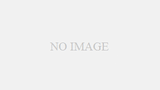アニメ「鬼滅の刃」でも日本刀は、鬼に対抗する武器になります。
世界最強の刃物とも言われる日本刀は、鉄を極限に鍛え上げ適度なしなりをもつことで最強の切れ味を出しているとも言われています。
本物の日本刀を作り続けた5大日本刀生産地
日本刀を作っていた町は、現代の日本で今も「刃物の町」として生き続けています。
中でも有名な生産地には、「五箇伝」と呼ばれる、日本刀製造の5つの流派が存在していました。
5つの流派は、切磋琢磨しながら技術を磨き5つの伝法を継承していきました。
5つの伝法とは、「大和伝」(現在の奈良県)、「山城伝」(現在の京都府南部)、「備前伝」(現在の岡山県南東部)、「相州伝」(現在の神奈川県)、「美濃伝」(現在の岐阜県南部)と言われています。
「大和伝」(現在の奈良県)
「大和伝」(現在の奈良県)は、最古の刀剣の制作地として名を馳せました。
神代鍛冶のひとりで刀匠の祖とされる天国(あまくに)は大和国の人と伝えられ、以来大和国では連綿(たえることなく、みゃくみゃく)と作刀が続けられ、国宝・重要文化財をはじめとする数々の名刀が産み出されてきたといいます。
奈良県は、奈良県北葛城郡当麻町の当麻寺に所属する刀工集団の「当麻派」や、若草山(奈良県奈良市)の麓に在住した刀工一派の「千手院派」など、「大和鍛冶」と呼ばれる数多くの刀工集団を輩出しました。
奈良県春日大社の「春日大社国宝殿」は、春日大社が所有する国宝354点及び重要文化財2526点を主に多数の文化財を所蔵し展示する美術館です。

「山城伝」(現在の京都周辺)
山城伝は、平安時代中・後期以降、山城地方(現在の京都周辺)に発生した名工や刀工集団による鍛法です。
794年の平安京遷都により山城国は、日本の中心地として繁栄し、平安時代初期には坂上田村麻呂の蝦夷征伐、平将門と藤原純友の乱(承平・天慶の乱)など多くの戦乱があり、山城国には武士団が形成されました。
政治的・軍事的中心であった平安京のある山城国では、刀工の需要が高く、こうした背景から山城国では作刀技術が発展し、刀剣製作の中心地となりました。

「備前伝」(現在の岡山県南東部)
平安後期から武士の台頭と共に刀剣需要が高まる中、備前国(現:岡山県南東部)は良質な砂鉄に恵まれ、刀剣生産の中心地となりました。ここで生まれた様式が「備前伝」です。
鎌倉時代には、相次ぐ争乱で刀剣技術が飛躍的に向上し、日本刀の歴史上最も優れた作品が多く生まれました。この時期、備前で特に栄えたのが福岡一文字派で、華麗な丁子乱れの刃文を持つ太刀で知られます。
室町時代に入り、応仁の乱で打刀が主力武器となると、その需要はピークに。備前長船には「鍛冶屋千軒」と呼ばれるほど多くの刀工が集まり、日本刀の黄金時代を支えました。
「相州伝」(現在の神奈川県)
相州伝は、鎌倉時代末期に相模国(現在の神奈川県)で確立された刀剣の刀工集団です。
鎌倉幕府の名により集められた、刀鍛冶は、大陸の新技術を取り入れ、従来の刀剣にない実用性と強度を追求しました。刀は地鉄(じがね)が黒ずんで板目(いため)肌がよく詰まり、湾れ(のたれ)や皆焼(ひたつら)といった大胆な刃文が見られます。
激しい戦乱に対応する折れにくく、曲がりにくい堅牢さから、武士に絶大な人気を博し、日本刀の歴史に名を刻みました。
後に、「正宗」(まさむね)によって、相州伝は、最高の名刀を世に送り出していきます。
「美濃伝」(現在の岐阜県南部)
美濃伝は、鎌倉時代中期に、良質の焼刃土を求めて、九州から来住したと伝わる元重に始まると伝わっています。しかし、事実上の美濃鍛冶の祖は、南北朝時代初期に、大和国より美濃国の志津へ来住した、正宗十哲(相州伝・正宗の十工)の一人である志津三郎兼氏であると謳われています。
南北時代中期には、北陸から金重が美濃国の関へ来住して、相州伝をもたらします。
志津三郎兼氏により、もともと大和伝系であった美濃国の作刀方式に、金重の相州伝が加味され、新たな作風が生まれ、これが美濃伝の礎となりました。
南北朝・戦国時代の争乱の時代に入ると、相州伝は、急速に繁栄しました。
日本刀の材料、玉鋼はどう作られる?
鬼滅の刃でも鬼殺隊への入隊試験後「最終選別」を突破した者に鬼を倒す唯一の武器、日輪刀の材料となる玉鋼を選ばせますね。
実際の日本刀の制作にも、すぐれた玉鋼(たまはがね)が材料として欠かすことが出来ません。
この玉鋼を作るには、これまた、日本の伝統的技術のたたら吹きによらなければなりません。
しかし、大正14年(1925)にたたらの火はすべて消え、その後、昭和8年(1933)から20年(1945)まで、仁多郡横田町大呂(おおろ)の安来製鉄鳥上工場内に、玉鋼製造のため、「靖国鑢(やすくにたたら)」が付設され、操業されていましたが、これも戦後に操業停止されました。
重要美術品、文化財としての日本刀の材料玉鋼の在庫品不足から、日本美術刀剣保存協会(略称、日刀保)が、旧靖国鑢の施設を復元して昭和52年(1977)11月に操業を開始したのが日刀保たたらです。
日本刀の名刀と呼ばれるものとは 天下五剣
天下五剣は、数ある日本刀のなかで最高傑作と言われている刀剣のことをいいます。
・大典太光世(おおてんたみつよ)
・鬼丸国綱(おにまるくにつな)
・数珠丸恒次(じゅずまるつねつぐ)
・童子切安綱(どうじぎりやすつな)
・三日月宗近(みかづきむねちか)
日本刀の切れ味に直結 日本の砥石
日本刀の切れ味に直結するのが、研師と砥石です。
鬼滅の刃のアニメでは、刀鍛冶の鋼鐵塚蛍さんが炭治郎の刀を超丁寧に研いでいますね。
ドラゴンボールの「元気玉」ほどではありませんが、まぁタメにタメてるのか?っと思いましたね。
どんな名工の日本刀も美しく仕上げるためには、研ぎの工程が必要です。
日本刀を最高級の美術品に昇華するためにはとても大切な工程なのです。
日本刀の研ぎでは、下地研ぎで6つ、仕上げ研ぎでも3つなど複数の砥石を使います。
日本刀の生産地に付随するように周辺で良質な砥石の生産も行われています。
日本国内の砥石生産地
日本には、多くの良質な砥石の生産地があります。
京都府 亀岡
合砥(あわせど):仕上げ砥石として最高級とされ、特に亀岡市で採掘されるものが有名です。
青砥(あおと):中砥石として、亀岡市では「丹波青砥」が採掘されます。
京都・亀岡は、太古の地殻変動の恵みをうけた天然砥石の聖地です。
亀岡産の良質な丹波青砥や合砥は、その繊細な研ぎで、和食や日本刀、和風建築など日本文化を支えてきました。
愛媛県
伊予砥(いよと)は、荒砥や中砥として使用されます。
日本で一番初めに流通したと言われる伝統ある天然砥石。
砂岩が固まってできた石で、研ぎだすと細かい粒が出ます
群馬県
虎砥(とらと)や沼田砥(ぬまたと)は、荒砥や中砥として使われます。
群馬県南牧村民俗資料館には砥沢の砥石に関する資料や江戸時代の絵図、100丁程の砥石の展示があり、砥石ファンには必見とのこと。
熊本県 天草
天草砥(あまくさと)は、中砥として知られています。
熊本県天草産の天然砥石は、凝灰石で、品質日本一を誇っています。
愛知県 三河
三河白名倉砥(みかわしろなぐらど)は、名倉砥として使われます。
愛知県北設楽郡三輪村で採掘されます。
三河白砥石は白名倉として知られる愛知県原産の天然砥石です。
長崎県 対馬
対馬(つしま)の黒名倉砥(くろなぐらど)は、名倉砥として使われます。
対馬砥石は長崎県の沖にある対馬の特産品
対馬黒名倉の大判で刃物もそのまま当てられる大きさの品が対馬砥石です。
兵庫県
但馬砥(たじまど)は、荒砥や中砥として使われます。
和歌山県
大村砥(おおむらと)は、荒砥として知られていましたが、現在は採掘終了しています。